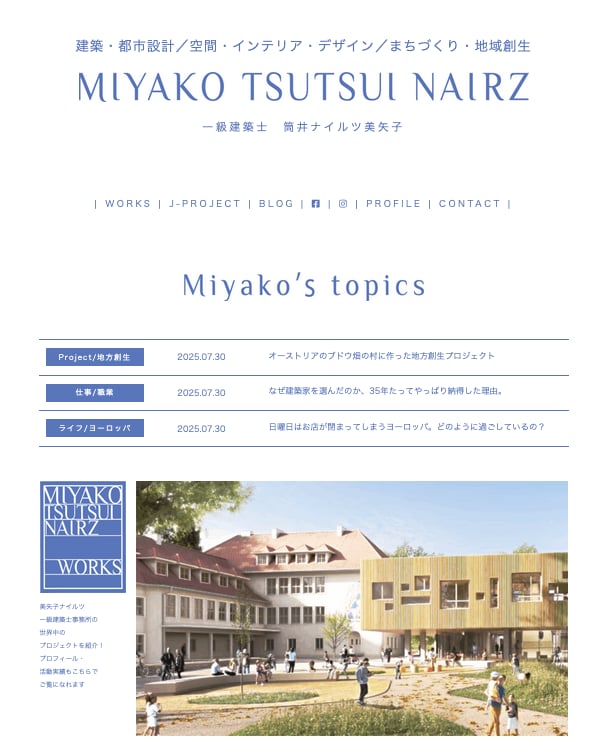EVENT
最新のイベント

講演アーカイブ視聴のお申し込み受付
パナソニック美術館「ウィーン・スタイル展」連動企画
「展覧会に行く前に(行った後も!)ちょっとだけ勉強をすると芸術が、ウィーンがもっと楽しく、理解できる」シリーズ第一弾!(日時 11月2日(日)20時-21時、ZOOM)
好評のうちに終了いたしました。ご参加の皆様ありがとうございました!
イベント終了後もアーカイブ視聴へのお申し込みが多いため、今回は特別に、今からお申し込みをされる方にもアーカイブ視聴のリンクをお送りしております。
お申し込みは「お申し込み」のボタンから。
「ウィーン・スタイル展」(汐留パナソニック美術館にて12/17まで)および講演内容については下記のイベント内容をご覧ください。
ウィーン・ヨーロッパの歴史・文化がわかる非常に面白い展示会です。また多くのプライベート・コレクションが出展されているため、この展示会でしか見られない貴重な展示品の数々は必見です!
イベント情報(11月2日夜8時〜ZOOM配信アーカイブ有り)「展覧会に行く前にちょっとだけ勉強をすると芸術が、ウィーンがもっと楽しく、理解できる」シリーズ第一弾!
現在、パナソニック汐留美術館で12月初旬まで行われているウイーンの芸術に関する展覧会
「ウィーン・スタイル展-ビーダーマイヤーと世紀末」
日頃見ることができない貴重なプライベート・コレクションの数々がウイーンより日本に来ています。
クリムト、オットー・ワーグナー、アドルフ・ロース…そして今回の目玉は、この時代よりさかのぼること100年前に花開いたビーダーマイヤー時代にデザインされた食器、工芸品、ファッション、装飾品なども見ることができます。この2つの時代を同時に展示していることにとても大きな意味があるのです。アートとともにその時代背景を追っている貴重な展示会です。
でも、世紀末って?ビーダーマイヤーって何?
展覧会ではたくさんの説明がしてありますが、その場ですべてを理解するのは大変!
大体その時代背景を知らないし…そもそもウイーンの歴史をどれだけ知っていたかしら…
という方も多いのではと思います。それではもったいない!
この素晴らしい展覧会をより楽しく・より深く理解するために、ウイーン在住の建築家・筒井ナイルツ美矢子が今回の展覧会の対象となる時代のウイーンの歴史・文化・建築をわかりやすくお話しします。そのあとに、展覧会を訪れれば、さらに理解が深まり、楽しく拝観できます!
日時 11月2日(日)20時-21時
場所 ZOOMによる視聴(申し込みの方に視聴方法をお知らせします)
参加料 無料
この日時に参加できない方は期間限定でアーカイブ視聴できますので、その旨を申し込み時にお知らせください。ZOOMでお会いできることを楽しみにしています!
筒井ナイルツ美矢子
現在、パナソニック汐留美術館で12月初旬まで行われているウイーンの芸術に関する展覧会

「展覧会に行く前にちょっとだけ勉強をすると芸術が、ウィーンがもっと楽しく、理解できる」シリーズ第一弾!
現在、パナソニック汐留美術館で12月初旬まで行われているウイーンの芸術に関する展覧会
「ウィーン・スタイル展-ビーダーマイヤーと世紀末」
https://panasonic.co.jp/ew/museum/exhibition/25/251004/
日頃見ることができない貴重なプライベート・コレクションの数々がウイーンより日本に来ています。
クリムト、オットー・ワーグナー、アドルフ・ロース…そして今回の目玉は、この時代よりさかのぼること100年前に花開いたビーダーマイヤー時代にデザインされた食器、工芸品、ファッション、装飾品なども見ることができます。この2つの時代を同時に展示していることにとても大きな意味があるのです。アートとともにその時代背景を追っている貴重な展示会です。
でも、世紀末って?ビーダーマイヤーって何?
展覧会ではたくさんの説明がしてありますが、その場ですべてを理解するのは大変!
大体その時代背景を知らないし…そもそもウイーンの歴史をどれだけ知っていたかしら…
という方も多いのではと思います。それではもったいない!
この素晴らしい展覧会をより楽しく・より深く理解するために、ウイーン在住の建築家・筒井ナイルツ美矢子が今回の展覧会の対象となる時代のウイーンの歴史・文化・建築をわかりやすくお話しします。そのあとに、展覧会を訪れれば、さらに理解が深まり、楽しく拝観できます!
日時 11月2日(日)20時-21時
場所 ZOOMによる視聴(申し込みの方に視聴方法をお知らせします)
参加料 無料
この日時に参加できない方は期間限定でアーカイブ視聴できますので、その旨を申し込み時にお知らせください。
ZOOMでお会いできることを楽しみにしています!
筒井ナイルツ美矢子

開催日:2025 年 4 月 30 日(水)
会場:リブコンテンツ
主催:筒井ナイルツ美矢子&谷口令
取材:編集・ライター S.T


筒井ナイルツ美矢子さんによる講演では、
ウィーンの歴史的建築と現代空間の融合手法
建築家としてだけでなく施主と向き合う対話の重要性
住まいづくりを通じてその人の「なりたい人生」を共に設計するプロセス
といったテーマが、数々の実例とスライドを交えて紹介されました。特に「空間は完成後もお施主さんに育ててもらう」という言葉が印象的で、参加者のクリエイティブな思考を刺激しました1. はじめに:ウィーンと建築家としての歩み
筒井ナイルツ美矢子さんのキャリア紹介
ウィーンでの35年間の活動歴、代表的プロジェクト(住宅リノベーション/公共施設設計)
日本と欧州を結ぶ架け橋としての立場
2. 空間づくりのステップ
ヒアリング
施主の「理想の暮らし」「日々のルーティン」「ライフストーリー」を深く対話で掘り下げる手法
コンサル
施主の不安を取り除くプロとして助言
3. 実例紹介
Case Study 1:そこに暮らす方のライフスタイルを重要視したプロジェクト
Case Study 2:施主の夢を叶えるための手法を日本のプロジェクトチームとの成功事例
4. 施主との“対話”がもたらす効果
単なる設計図のやり取りではなく、ワークショップ形式でアイデアを共有
心理的安心感の対話が、施主の本質的ニーズを引き出すプロセス例
5. まとめ:日本プロジェクトのこれから
不安を無くし夢を叶えるプロジェクトを現実化する
参加の夢を引き出すこれからのイベントを紹介
次回開催への夢:ウィーン視察ツアー
このように、“空間を育てる”ための具体的手法や、ヨーロッパならではの考え方やワークショップ型ヒアリングの事例が盛り込まれ、大変実践的かつ示唆に富んだ講演内容でした。
受講生からの感想1
本日は素晴らしいセミナー企画をありがとうございました。
ミヤコさんはお仕事の進め方が独創的でとてもクリエイティブ脳を刺激されました。
ただ空間を作るだけでなく、その後もお施主さんに空間を育ててもらう。とても印象的な言葉でした。
谷口先生がおっしゃるように世界的な建築家なのに何故か親しみやすくお話を聞いていて益々、ミヤコさんの魅力に引き込まれました。
こんなセミナーがあったら受講してみたい: 今日の事例紹介は出来上がった空間の素晴らしさも去ることながらそこに行き着くまでのストーリーや背景がとても面白かったですので第二弾を楽しみにしています。
受講生からの感想2
家を作るということは間取りを作るだけではなく、その人のなりたい人生を作るために時間をかけて対話するということに感銘を受けました!
どのような仕事でも、根底にあるものは同じなのだなと共感しました。
貴重なお話しをありがとうございました。
受講生からの感想3
まるでウィーンを旅行しているような楽しくて、ワクワクするセミナーをありがとうございました。
まずはどう暮らしたいのか?
どう生きたいのか?
それをはっきりさせることが何より大切だとつくづく思いました。
こんなセミナーがあったら受講してみたい: 今日のようなセミナーは、気分も新たになりますので、ぜひまた参加したいと思います。
受講生からの感想4
今日は有難うございました。
ウィーンのお菓子や紅茶、コーヒーをいただきながら美矢子さんのお話しを伺うことができてあっという間の時間でした。もっと聞きたかった位です。
受講生からの感想5
ウィーンの歴史的建造物がどのように維持されているか、いかにウィーンの人々に愛されて大切にされ、日常生活に溶け込んでいるか、大変興味深いお話でした。そして、施主の想いをいかにして形に空間を作っていくのか、もはや美也子さんは建築家でありながら、セラピストのような方だな、と思いました。自分の好きや、大切にしていること、信念。これらを常に意識して生きていく事が改めて大切だと感じました。
『空間は人生を映し出す鏡──ウィーンから届いた、美の哲学』
その午後、自由が丘の一角にある洗練されたギャラリー空間「リブコンテンツ」は、まるでウィーンのカフェ・ザッハーの一室に変わっていた。
カーテン越しに差し込む春の光。どこか遠くでバイオリンの音が聞こえてきそうな錯覚。
そして、目の前には、35年もの間ウィーンで暮らし、世界で建築と向き合ってきたひとりの女性、建築家・筒井ナイルツ美矢子さんがいた。
この日行われたのは、「ウィーンで暮らし、世界で仕事をする」というテーマを軸に、筒井さんの人生と建築観、そして住まいづくりの哲学に触れる特別セミナー。
一見、よくある建築セミナーかと思われるかもしれない。しかし、それはまったく違っていた。
これは、人生をどう設計し、どう生きるかという壮大な問いを、空間という“静かな舞台”を通じて描く、ある種の人生劇だったのだ。
冒頭、筒井さんの語り口はとても穏やかで、けれど凛としていた。
「私は、空間を“完成させる”ために建築しているわけではありません。住む人が、そこに命を吹き込む余白を残したいのです」
その言葉を聞いた瞬間、私はハッと息を呑んだ。
彼女が見せてくれた数々の事例写真。そこには、ウィーンの歴史的な街並みに馴染みながらも、どこか柔らかい日本の気配を感じる空間があった。
「この壁の凹みには、施主さんが子どものころに使っていたピアノの譜面台を埋め込みました。毎日そこを見ることで、過去と未来がつながるように」
まるで映画のワンシーンのように、空間の細部にストーリーが宿っている。彼女の手がけた家には、図面に描かれていない“記憶”と“夢”が刻まれているのだ。
参加者たちはウィーンの焼き菓子と本格コーヒーを片手に、彼女の言葉に耳を傾けた。
甘くて少しほろ苦いケーキを味わいながら、私たちは「空間とは、五感で味わうものだ」ということを、改めて思い出す。
建築とは、単なる設計行為ではない。それは、香り、音、手触り──暮らしの“質感”すべてをデザインする、壮大なアートなのだ。
印象深かったのは、筒井さんが何度も強調していた「対話の力」だった。
「家を建てる前に、まずはたくさん話します。どんなふうに起きて、どんな音楽が好きで、何に癒されるか──その人の人生を知り尽くしたうえでなければ、空間は提案できません」
私は心の中で頷いた。今、多くの人が求めているのは“オシャレな家”ではなく、“私の物語を包んでくれる場所”なのだ。
質疑応答の時間になると、会場から次々に手が挙がった。
「海外で仕事を続ける上で、大切にしていることは?」「日本とウィーンの建築の違いは?」
その一つひとつに、筒井さんは丁寧に、そして愛情をこめて答えていた。
彼女の言葉の奥には、異国でキャリアを築くことの孤独や、そこを乗り越えた者だけが持つ凛とした誇りが滲んでいた。
講演の最後に、彼女はこう語った。
「空間をつくるということは、その人がどんな人生を送りたいかを問うこと。だから、私は一つとして同じ家をつくったことがありません」
その言葉は、私たちにこう問いかけているようだった。
──あなたは、どんな人生を“育てたい”のですか?と。
セミナーが終わった後も、参加者たちはその場を離れがたく、ひとりひとりが筒井さんと話をしようと列をなしていた。
その姿は、まるで一本の感動作を観終えた観客たちが、まだ心の奥で物語の余韻を味わっているかのようだった。
あの日、自由が丘に現れた小さな“ウィーン”は、確かに私たちの人生観に静かな革命を起こした。
「住まいは、私たち自身の内面を映し出す鏡」。
筒井ナイルツ美矢子さんのセミナーは、建築を超えて、私たちがどんな“自分”として生きていきたいのか──その問いを優しく、しかし確かに私たちに投げかけていた。
編集・ライター S.T